FB上で「7日間ブックカバーチャレンジ」なるものが展開されてますね。
「読書文化の普及に貢献するためのチャレンジで参加方法は好きな本を1日1冊、7日間投稿する」というもので、ルールは①本の説明はなしで表紙画像だけアップ、②その都度1人のFB友達を招待し参加をお願いする。
ですが、ルールから外れて最近読んだ本7冊の紹介と説明までしてしまいます。
1。日本史の謎は地形で解ける 竹村公太郎
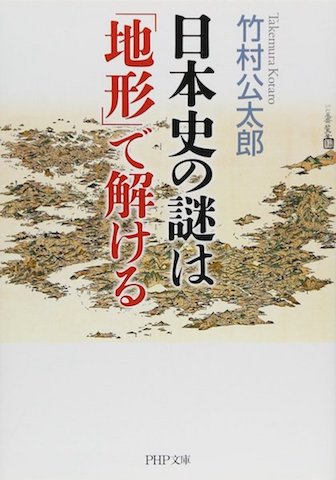
歴史の専門家はたいてい文系であり人文社会的で人文解釈は多様なものになりがち、結局決め手がないまま果てしなく議論が続くが、筆者は元建設省の技師で地形、気象、インフラなど下部構造から歴史の謎にアプローチする。
これがすこぶる面白い。
日本文明を生んだ奈良はなぜ衰退したか? 関ヶ原勝利後なぜ家康はすぐ江戸に戻ったか? などなど建築にも通じるネタが満載。これを読むと家康がいかに先見の明がある政治家、都市計画家だったがわかる。
2。センスは知識から始まる 水野学

ご存知、筆者はくまモン生みの親。
センスとは、「数値化できない事象を評価し、最適化する能力」だと。そしてそのセンスは決して先天的なものではなく、知識を蓄積することで得ることができるのだと。娘たちにも勧めている1冊です。
3。住宅 安藤忠雄

建築家安藤氏による住宅論。
住宅設計は「時代」と「人間」に何よりもリアルに触れることができる非常に良い仕事だと。施主も熱心だから本気で取り組まねばならないし、相手より勉強しないと自分の考えていることを説明できないし説得力もないから、住宅を通して建築を学ぼうという姿勢は今もって変わらないと書いている。
こんな時期だからこそよいタイミングでじっくり再読できた。
4。「いき」の構造 九鬼周造

昔、建築家の長老諸先輩方から勧められて読んだときは哲学者の言葉が難解でおそらく何割かして理解できてなかった。
「いき」というもの概念の力によって明確化し構造化するにあたり、内包的見地や外延的見地から外堀を埋め、自然的表現や芸術的表現から探っていく、(苦)
「いき」とは身振りや髪型だけで、あるいは色や柄だけで「いき」が何であるかを語ることはできず、背後には長い歴史と文化の蓄積とがある。色でいえば例えば鼠色や褐色が「いき」であるのは、華やかな体験に伴う消極的残像で、過去を擁して未来に生きているのだと。
さらには、対象の一元的均衡が打破され二元性が措置されており、その均衡の打破が徹底したものではなく、抑制と節度をもったものであることによって「いき」の表出が可能になるのである。
建築でいえば材料や空間の二元性。例えば天井には丸竹や黒褐色の杉皮とし、床は青畳として対立関係を図るなど。
これは一生かけて読み続けるべきかな。
5。勝負の心得 立浪和義
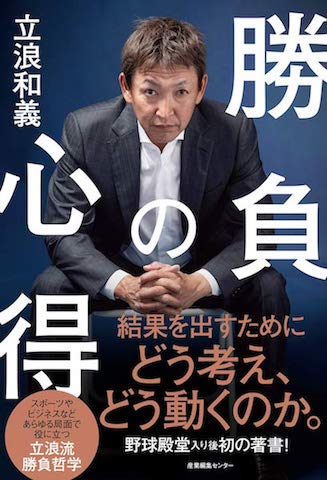
元ドラゴンズ立浪の著書。
通算2480安打。487二塁打は日本プロ野球史上いまだ破られていない大記録。
そんな立浪氏が、「打者は3割打てば一流、逆に言えば7割は失敗」「反省すべきことは多く、振り返りノートをつけたていた」というのが印象的だった。
野球に興味がなくてもおすすめできる一冊。
6。陰翳礼讃 谷崎潤一郎
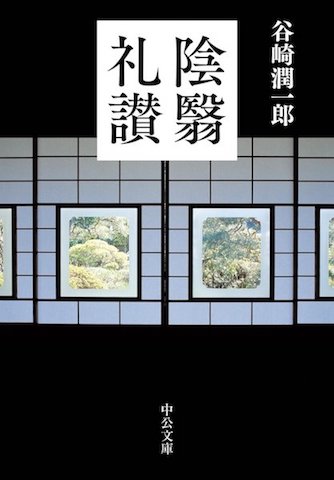
こちらも建築やってる人の必読書で今回再読。
建築に触れている印象的な一節を紹介。
建築においては屋根という傘を広げて大地に一廓の日かげを落とし、その薄暗い陰翳の中に家造りをする。西洋のそれは帽子でしかない。暗い部屋に住むこと余儀なくされた我々の先祖はいつしか陰翳のうちに美を発見し、やがては美の目的に添うように陰翳を利用するに至った、、、
7。ロンシャン 光の礼拝堂 イヴ・ブーヴィエ + クリストフ・クザン

2016年9月に訪れたコルビュジェ設計のロンシャン礼拝堂。
設計仲間5人で巡った旅の記録はこちら
ロンシャンの丘に建つ巡礼地としての礼拝堂は東にヴォージュ山脈、西にソーヌ川平野を望む水平線の風景がある。
この建築はアカデミックな方式によって取り決められるものではなく、ゆるやかで不均整、正に自由で千変万化なものとして4つの水平線に調和しており、訪問者を深淵へと導いている。
建築物を覆っているのは印象的なコンクリートの甲羅。南側と東側の窪んだ壁は外部に開き訪問者を迎え入れ、西側と北側の2つの壁は内側に巻かれくつろいだ空間を作り出す。
内部へ入ると薄暗がりの中にまばゆい白い光の印象が支配する。アーチ型の天井は存在感があり天井際のスリットから入る光のラインがこれを強調しており、南側の壁にも東側の壁に接していないがわかる。
光を振動させるほど荒々しい表面の白い壁、巡礼のときのみ開かれる原色のエナメル塗りを施した鋳鉄の大きな扉、印象的なガーゴイル、モデュロールに基づく空間構成、地形をなぞるように傾斜する床と丸い天井との共働作用、日光の効果をコントロールすべく壁の厚みなどなど。
コルビュジェ自身は過去の旅を体験するなかで、その場所ごとの特質を識別し、景観の力を利用することに配慮し、自然環境に共鳴する建築的景観を形作ることに注力した。アクロポリスでのパルテノン神殿、フランスのトロネ修道院訪問でみた修道士の戒律の厳しさ、東方トルコでみた聖テオドール聖堂の偉大な再現、アルジェリアの砂漠の中のガルダイアの建築にみた中庭と内部の諸空間の配置など、旅で得た構想は枚挙にいとまがない。
嗚呼、自分も旅に出たい。。。。。。。。